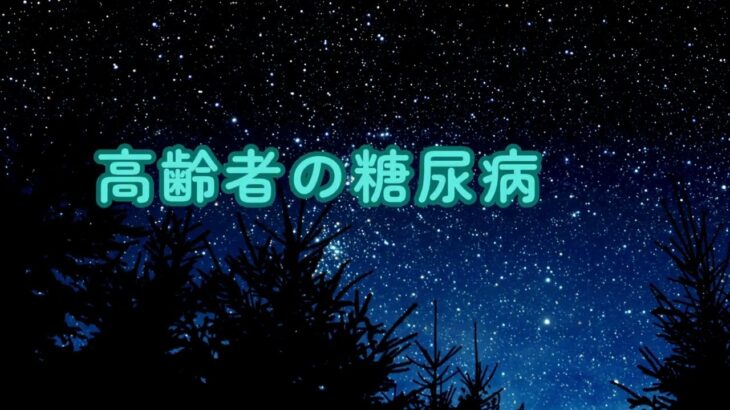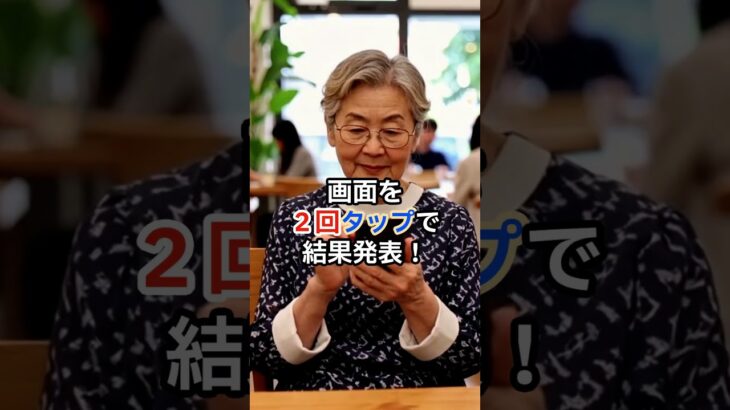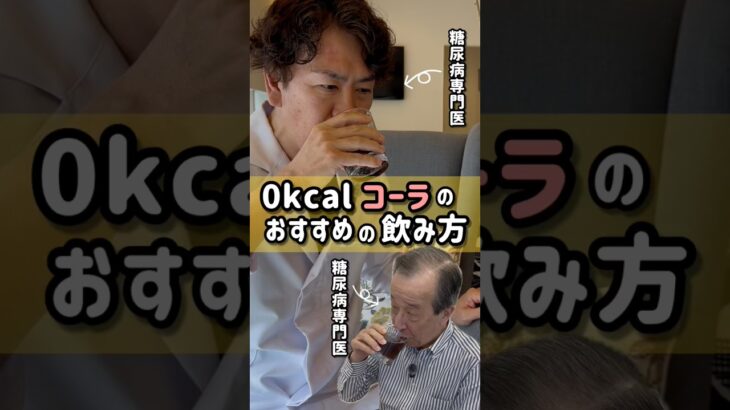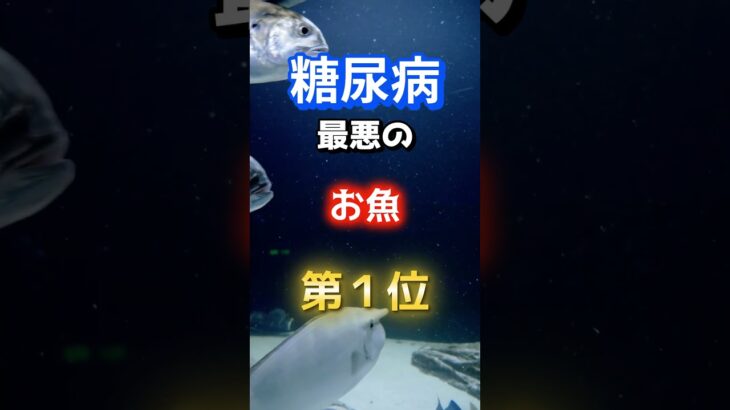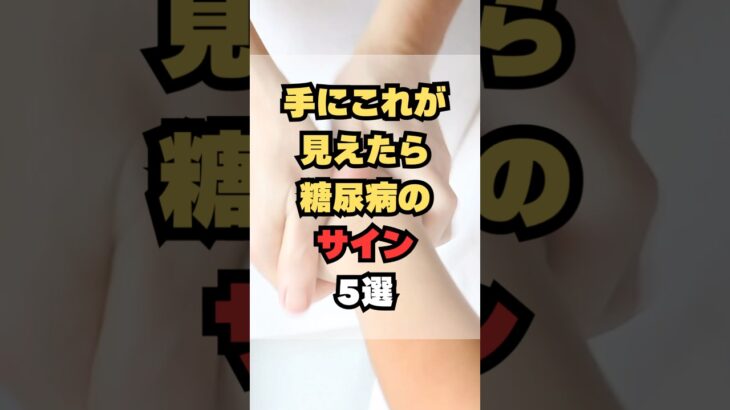高齢者の糖尿病
高齢者の糖尿病治療では、認知機能、ADL(日常生活動作)、併存疾患、重症低血糖のリスクなどを総合的に評価し、個別の治療目標を設定することが重要です。
1.高齢者糖尿病の特徴と治療上の注意点
高齢の糖尿病患者さんでは、以下の点に特に注意が必要です。
身体機能・認知機能の低下:ADL低下、認知機能低下、サルコペニア(筋肉量および筋力の低下)、フレイル(加齢に伴う心身の脆弱化)を合併しやすく、これらが血糖コントロールや自己管理能力に影響を与えることがあります。
併存疾患の多様性:多くの併存疾患(高血圧、脂質異常症、骨粗鬆症、脳血管障害、心疾患など)を持つことが多く、多剤併用となる傾向があります。
低血糖のリスクと影響:重症低血糖は、認知機能のさらなる低下、心血管イベントのリスク増加、転倒・骨折、QOL(生活の質)低下につながるため、特に避けるべきです。無自覚性低血糖も起こりやすいです。
栄養状態:食欲不振や低栄養状態にも注意が必要です。
サポート体制:家族や介護サービスのサポート状況も治療計画に影響します。
2.高齢者糖尿病の血糖コントロール目標(HbA1c値)
血糖コントロール目標は、年齢、罹病期間、臓器障害、低血糖の危険性、サポート体制などを考慮して個別に設定されます。特に高齢者では、認知機能とADL、および使用薬剤(低血糖リスクが高い薬剤の使用有無)によってカテゴリー分類され、目標値が異なります。
カテゴリーⅠ(認知機能正常、ADL自立):
・重症低血糖が危惧される薬剤(インスリン、SU薬、グリニド薬など)の使用なし:HbA1c 7.0%未満
・重症低血糖が危惧される薬剤の使用あり:HbA1c 7.0%未満(下限6.5%)
カテゴリーⅡ(軽度認知障害~軽度認知症、またはADL低下はあるが基本的なADLは自立):
・重症低血糖が危惧される薬剤の使用なし:HbA1c 7.0%未満
・重症低血糖が危惧される薬剤の使用あり:HbA1c 8.0%未満(下限7.0%)
カテゴリーⅢ(中等度以上の認知症、またはADLが著しく低下、多くの併存疾患や機能障害):
・重症低血糖が危惧される薬剤の使用なし:HbA1c 8.0%未満
・重症低血糖が危惧される薬剤の使用あり:HbA1c 8.5%未満(下限7.5%)
治療目標設定の注意点:
・適切な食事療法や運動療法だけで達成可能な場合、または薬物療法中でも低血糖などの副作用なく達成可能な場合は、より低い目標(例:HbA1c 6.0%未満)も考慮されます。
・治療強化が困難な場合は、より緩やかな目標(例:HbA1c 8.0%未満)とします。
・これらの目標は、重症低血糖のリスクを最小限にしつつ、合併症の発症・進展を抑制することを目的としています。
・75歳以上の後期高齢者では、フレイル、ADL低下、合併症、体組成、摂食状況などを踏まえ、目標値を適宜判断します。
3.高齢者糖尿病の治療における配慮点
個別化:治療目標や治療内容は、患者さんごとの状態に合わせて個別化します。
低血糖の回避:特に重症低血糖は厳に避ける必要があります。低血糖を起こしにくい薬剤の選択や、シックデイ時の対応などを丁寧に指導します。
薬物療法:
・SU薬やインスリン製剤は、低血糖のリスクが高いため慎重に使用します。少量から開始し、シックデイ時の休薬も考慮します。
・DPP-4阻害薬は、腎機能に応じて用量調節が必要なものと不要なものがあります。
・SGLT2阻害薬は、脱水、ケトアシドーシス、尿路・性器感染症に注意し、シックデイには休薬します。
多因子介入:血糖だけでなく、血圧、脂質、体重の管理、禁煙も重要です。
高齢者総合機能評価(CGA):身体機能、認知機能、心理状態、栄養状態、薬剤、社会・経済状況などを多職種で評価し、治療計画に活かします。
食事療法・運動療法:サルコペニアやフレイルの予防・改善のため、適切な栄養摂取(特にタンパク質)と、個々の状態に合わせた運動療法(有酸素運動、レジスタンス運動、バランス運動など)が推奨されます。
サポート体制の活用:服薬管理やインスリン注射が困難な場合は、家族のサポートや訪問看護、デイサービスなどの介護サービスの利用も検討します。
4.サルコペニアとフレイル
サルコペニア:加齢に伴う筋肉量および筋力の進行性低下。身体機能低下、QOL低下、死亡リスク上昇と関連します。
フレイル:加齢に伴い生理的予備能が低下し、ストレスに対する脆弱性が亢進した状態。健康障害を招きやすいです。
高齢糖尿病患者さんは、サルコペニアやフレイルを合併しやすい傾向にあります。
予防と対策には、適切な栄養(特にタンパク質の積極的摂取)、運動(レジスタンス運動や有酸素運動)、社会参加などが重要です。