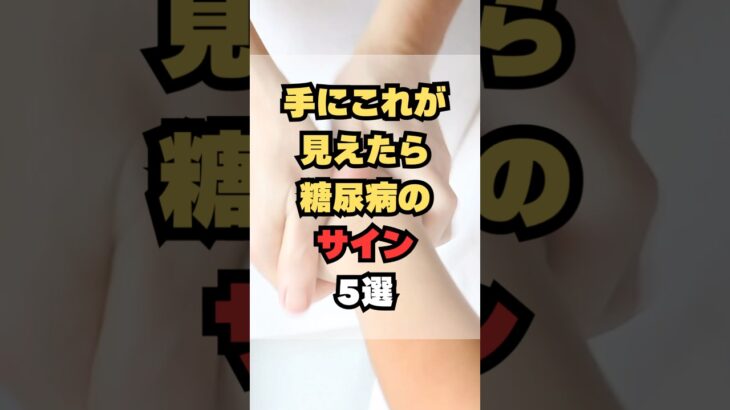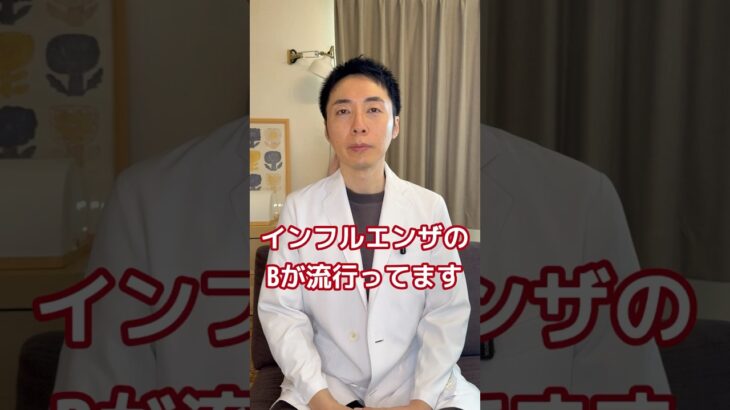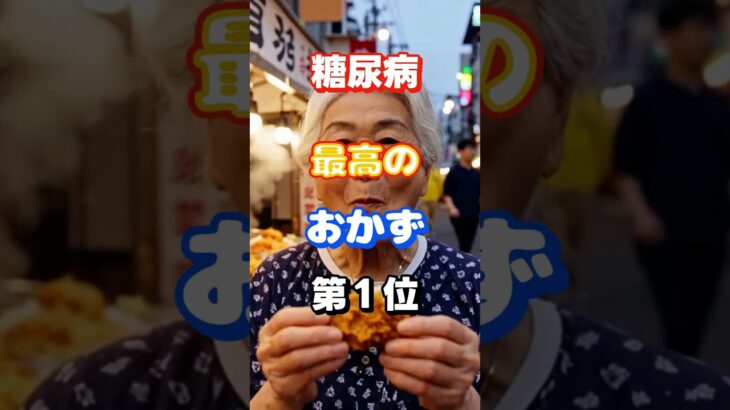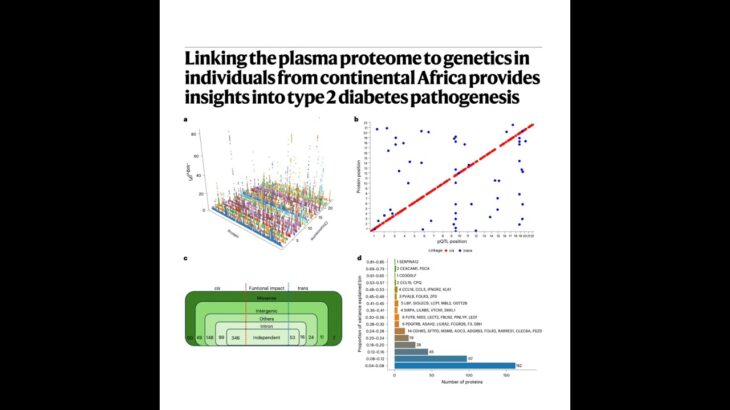糖尿病の運動療法
運動療法は食事療法と並び、糖尿病治療の基本の一つです。
1.運動療法の効果
・急性効果:ブドウ糖や脂肪酸の利用が促進され、血糖値が低下します。
・慢性効果:インスリン抵抗性が改善します。
・エネルギー摂取量と消費量のバランスが改善され、減量効果が期待できます。
・加齢や運動不足による筋萎縮や骨粗鬆症の予防に有効です。
・高血圧や脂質異常症の改善に有効です。
・心肺機能が向上します。
・運動能力が向上します。
・爽快感や活動的な気分など、日常生活の質(QOL)を高める効果も期待できます。運動には以下のような効果が期待できます。
2.運動療法の進め方
メディカルチェック:
・日常生活活動の範囲内(速歩など)の軽度〜中強度の運動であれば通常不要ですが、普段より高強度の運動を行う場合や心血管疾患リスクの高い患者さんでは、運動開始前にメディカルチェックが必要です。
・網膜症、腎症、神経障害などの合併症や整形外科的疾患の有無などを把握し、運動制限の必要性を検討します。
個別化:個人の基礎体力、年齢、体重、健康状態などに応じた適切な運動の種類、強度、時間、頻度を決定します。最初は歩行時間を増やすなど無理のない範囲から始め、段階的に運動量を増やします。
安全管理:運動前後の脈拍数や血圧の測定、自覚症状の確認が大切です。
継続性:患者さんの嗜好に合った運動を取り入れるなど、楽しさを実感できるよう工夫することが重要です。
座位時間の中断:日常の座位時間が長くならないようにし、30分を超えたら一度中断して軽い運動を行うことが勧められます。
効果判定とフィードバック:定期的に血糖、HbA1c、体組成、体力などを評価し、患者さんにフィードバックしながら継続を支援します。
3.運動の種類
有酸素運動:酸素を十分に取り込みながら行う持続的な運動で、インスリン感受性を高めます。例:歩行、ジョギング、水泳など。
レジスタンス運動:おもりや抵抗負荷に対して行う運動で、筋肉量を増やし筋力を増強します。例:腹筋、ダンベル、スクワットなど。
バランス運動:高齢者において、バランス能力を向上させ生活機能の維持・向上に有用です。例:片足立位保持、ステップ練習など。
有酸素運動とレジスタンス運動はともに血糖コントロールに有効で、併用によりさらに効果が高まります。水中歩行は両者の要素を併せ持ち、膝への負担が少なく肥満患者さんにも適しています。
4.運動の強度
中強度(ややきついと感じる程度)の有酸素運動が一般的に推奨されます。
・心拍数の目安:50歳未満では100~120拍/分、50歳以上では100拍/分未満。
・不整脈や自律神経障害がある場合などは、自覚的なきつさ(「楽である」または「ややきつい」)を目安にします。「きつい」と感じる場合は強すぎる可能性があります。
・METs(メッツ):安静時を1とした運動強度の単位。中強度は3METs程度(例:普通の速さのウォーキング、軽い筋力トレーニング)。慣れてきたらやや強い強度(4~6METs)も考慮します。
※収縮期血圧が180mmHgを超えるような運動は避けるべきです。
5.運動時間と頻度
有酸素運動:中強度で週に150分以上、または週に3回以上、運動しない日が2日間以上続かないように行います。1回20分以上の持続が糖質と脂肪酸の効率的な燃焼に望ましいです。
・歩行運動の場合、1回15~30分間を1日2回、1日の合計歩数は約1万歩程度が適当です。
レジスタンス運動:連続しない日程で週に2~3回行うことが推奨されます。
日常生活活動:特別な運動時間を設けられない場合でも、階段利用や通勤時の歩行など、日常生活の中での身体活動量を増やす(NEAT:Non-Exercise Activity Thermogenesis)ことが大切です。
6.運動の消費エネルギー
・消費エネルギー(kcal)=METs×体重(kg)×運動時間(時)
・運動で消費するエネルギーはそれほど多くないため、「運動した分だけ食事を増やせる」という考えは誤りです。運動療法は食事療法と組み合わせることで効果が高まります。(
7.運動療法指導上の注意点
・血糖コントロールが不安定な時は、運動強度と時間を控えめにします。
・運動実施のタイミングは食後1時間頃が望ましいとされていますが、実生活で可能な時間で構いません。
・インスリン療法やSU薬で治療中の場合は、低血糖に注意が必要です。運動中や直後だけでなく、十数時間後に起こることもあります。血糖自己測定を行い、必要に応じて補食やインスリン量の調整を行います。
・運動の影響を受けやすい四肢を避け、インスリンは腹壁に注射するのが原則です。
・準備運動と整理運動を励行します。
・適切な衣服、靴を選びます。
・歩数計や活動量計の活用はアドヒアランス向上に有効です。
・寒冷・暑熱環境下での体温調節に注意します。
・腰椎や下肢関節に疾患がある場合は、筋力トレーニングや水中運動などを検討します。
・高齢者では安全に配慮して実施します。
8.運動療法を禁止あるいは制限した方がよい場合
・血糖コントロールが著しく不良な場合(空腹時血糖値250mg/dL以上、または尿ケトン体中等度以上陽性)。
・増殖前網膜症以上の場合(眼科医と相談)。
・腎不全の状態にある場合(専門医の意見を求める)。
・虚血性心疾患や心肺機能に障害のある場合(専門医の意見を求める)。
・骨・関節疾患がある場合(専門医の意見を求める)。
・急性感染症。
・糖尿病性壊疽。
・高度の糖尿病性自律神経障害。
これらの場合でも、日常生活における体動が制限されることはまれで、必ずしも安静臥床が必要なわけではありません。特に糖尿病では無症候性心筋虚血に注意が必要です。