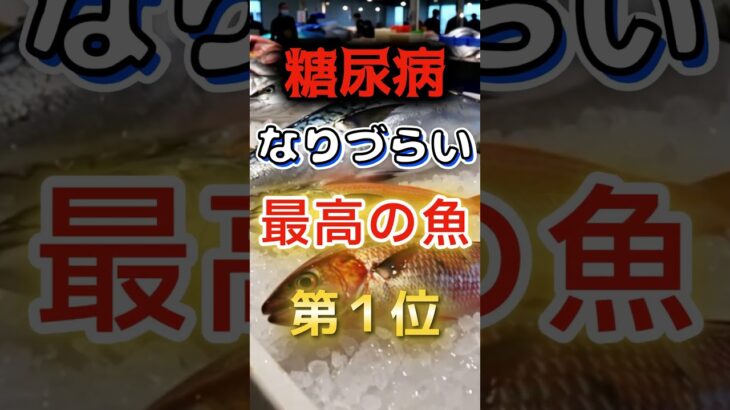時間栄養学 肥満と糖尿病 朝食を食べない方や夕食の時間が遅い夜型の生活は、中枢時計と末梢時計に時差ぼけが生じます。夜勤の方はなおさらです。時差ぼけでは、自由な時間に食事が出来るときに、肥満になります。
中枢時計をメラトニン分泌で、末梢時計もモニターし、食事時刻のみ5時間遅らせると、末梢時計のみ1.5時間程度遅れます。朝食を食べない方や夕食の時間が遅い夜型の生活は、中枢時計と末梢時計に時差ぼけを生み出します。夜勤の方はなおさらです。
通常は中枢末梢時差ぼけは、1.5時間から6時間程度ですが、昼夜逆転すると12時間になります。
消化器系の時計の同調因子は光の制御より強いことわかっています。食事は内臓において最も強い同調因子です。首から下のすべての臓器の時計の同調因子は食事が主役です。ですから朝ごはんを食べない方や夕食が遅い方は、やはり時差ぼけのままで生活することになります。
時差ぼけのマウスは、自由な時間に食事が出来るときに、肥満になります。
そのまま人間に当てはまるわけではないですが、今の世の中の現象を説明しているのではないでしょうか。一番最悪なのは、時差ぼけの上に、好き勝手な時間に食事をたべることです。昼夜逆転の引きこもりの場合に起きやすい現象です。
人間には、目には見えませんが、ホルモンの放出に関して正常なリズムが存在します。それが生体内時差ぼけによって狂います。
時差ぼけの状態では、コルチゾールが増加し、筋肉を減少させ、一様に疲労感と緊張感を訴え、カフェインへの依存を強めていく傾向があります。
カフェインは交感神経を刺激し、適度なカフェイン摂取は、集中力や作業効率の向上に繋がることが期待できますが、過剰摂取は不眠や不安感、動悸などの原因となる可能性があります。
時差ボケの解消にカフェインは有効な場合がありますが、カフェインは体内時計を調節するのに役立つ一方で、過剰摂取は睡眠など正常な日常のリズムを障害します。
マイオカインとは、筋肉から分泌される生理活性物質の総称で、BDNF(脳由来神経栄養因子)もその一つです。BDNFは脳の神経細胞の生存や成長を助ける因子として知られていますが、筋肉からも分泌され、マイオカインとしても機能します。特に、運動によって筋肉から分泌されるBDNFは、脳の機能を高める効果が期待されています。
体内時計の不調和
夕方以降にカフェインを摂取すると、体内時計の周期が遅れる傾向があります。甘味とカフェインを同時に摂取すると、体内時計が大きく遅れる可能性があります。
カフェインにもドーパミンに作用する働きがあり興奮作用や中毒性があると言われますが、カフェインは少し作用の仕方が異なっておりドーパミンを抑制するアデノシンという物質の働きを阻害することで、間接的に興奮物質ドーパミンの効果を強化しています。そのため、ドーパミンの放出を促す甘味と、ドーパミンの抑制を阻害するカフェインの組み合わせは、強力な相乗効果を生む可能性があります。
高脂肪食は、特に夜間の摂取が体内時計のリズムを乱す可能性が指摘されています。これは、高脂肪食が体内時計を調整する遺伝子の転写の働きを阻害するためと考えられています。高脂肪食は体内時計を伸長させ、リズムを減弱させることが示されています。これは高脂肪食により放出された胆汁酸が核内に入り込み、遺伝子に直接作用することからも理解できると思います。
マウスは夜行性です。 健康なマウスを、12時間明るい、12時間暗いという照明を繰り返す部屋で飼育しておくと、明るいときは休んで、暗いときに動きまわります。
マウスに高脂肪食を4ヶ月間与えた実験によると、いつでも好きな時刻に食べられるように与えた群と、活動期の8時間のみに制限して与えた群では、1日当りの摂取総量は同じでも、前者は典型的な肥満になり、後者はほとんど肥満にならないそうです。同じ量の食事であっても、摂取時刻によってエネルギー代謝に与える効果が異なることが知られています。ヒトの場合、朝食を抜く回数が多い、あるいは、夜食の頻度が高い人ほど肥満の傾向が強くなります。また、1日あたりの摂取カロリーをそろえたダイエット実験においても、朝食を多くして夕食を少なくした方が、その反対よりも体重減少効果が高くなります。
一方で、カロリー不足の状態や低炭水化物食では、体内時計の短縮や前進が報告されています。(早寝早起きなど時間の調節に利用できるかもしれません。)
概日リズムは体内時計の遺伝子転写リズムによって生み出されています。
時間栄養学は、食事のタイミングと体内時計の関係に着目し、健康や病気の予防に役立てる学問です。エビデンスとしては、食事のタイミングを整えることで、体内時計が正常に働き、生活習慣病のリスクを減らす効果が示唆されています。特に、朝食をしっかりとることで体内時計をリセットし、代謝を活発にすることが重要とされています。また、夜遅い時間の食事は、体内時計を狂わせ、肥満や生活習慣病のリスクを高める可能性があります。
時間栄養学 肥満と糖尿病 朝食を食べない方や夕食の時間が遅い夜型の生活は、中枢時計と末梢時計に時差ぼけが生じます。夜勤の方はなおさらです。時差ぼけでは、自由な時間に食事が出来るときに、肥満になります。
- 2025.07.23
- カテゴリー1