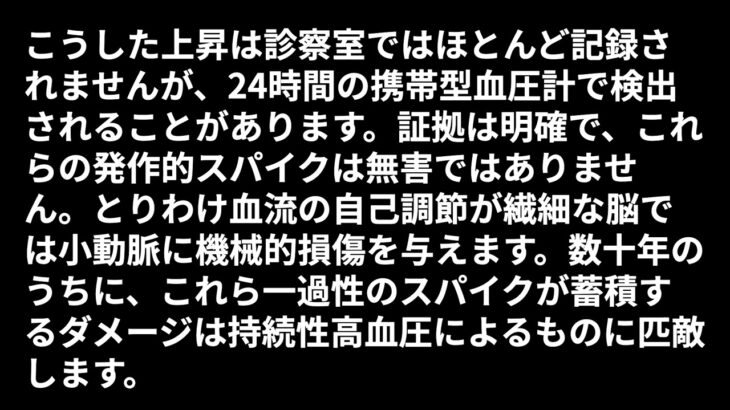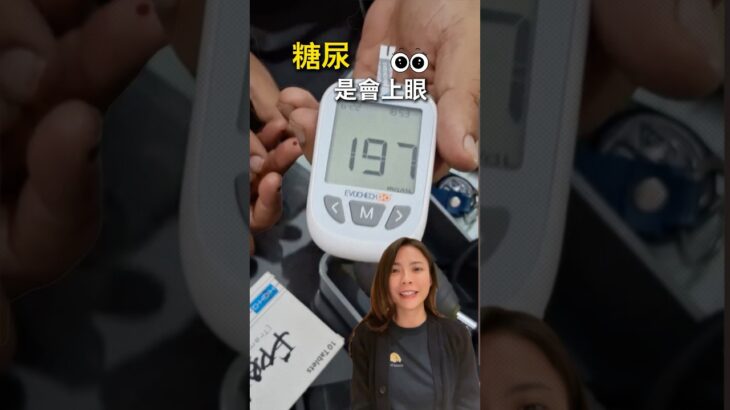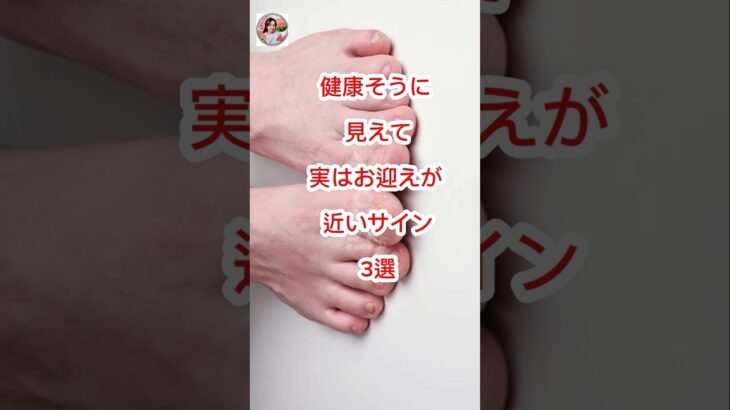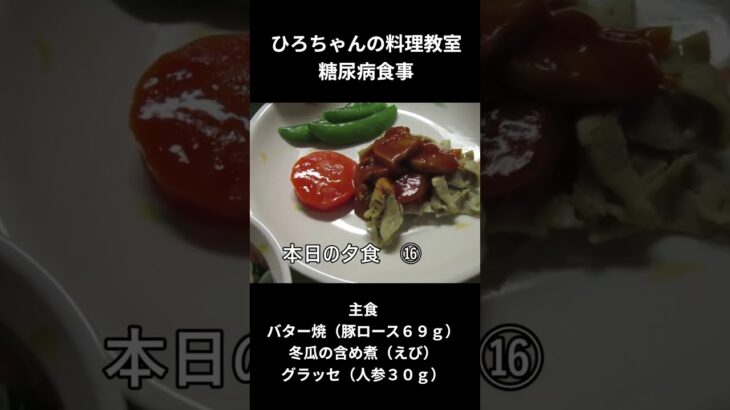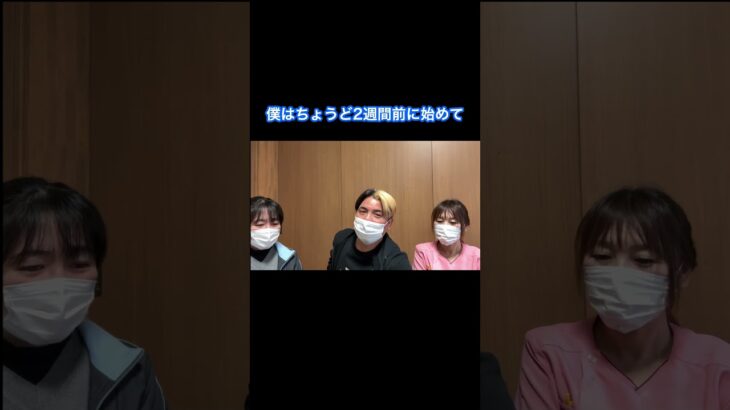糖尿病から高血圧を経て脳細胞の石灰化へ――脳細胞損傷の足跡
(No.1354、2025年9月11日)
ジェラルド・C・スー
EclaireMD財団
カテゴリー:糖尿病・高血圧・脳卒中
はじめに
2025年9月11日の午後、私はスタンフォード大学の脳卒中科部長ニール・シュワルツ医師と面談し、脳卒中後のフォローアップとしてCT画像とMRI画像を確認しました。そこで初めて、今回の出血性脳卒中の根本原因をはっきり理解しました。それは単一の引き金ではなく、2型糖尿病が30年以上続いたこと、慢性高血圧とは診断されていなくても断続的に起きていた急性高血圧のエピソード、そして脳の小血管内に見られた白い石灰化が、長年にわたって累積した結果でした。時間とともにこの組み合わせが脳の微小循環の回復力を弱め、ついには一本の血管がそのストレスに耐えられなくなったのです。
この気づきは、1972年にMITでジョーンズ教授の授業から学んだ「動的荷重下における構造物の非線形で塑性的(元に戻りにくい)応答」という概念と強く一致していました。
糖尿病とその長期的な血管影響
私は30年以上、2型糖尿病(T2D)とともに生きてきました。直近の15年は生活を厳格かつ自律的に管理し、薬を使わずにヘモグロビンエーワンシー(HbA1c)を5.8〜6.7の範囲に維持してきました。しかし、その前の20年間の不十分なコントロールは、血管系に確かな痕跡を残しました。医学文献はこの点で一貫しています。慢性的な高血糖は内皮機能障害、動脈硬化(動脈の硬化)、アテローム硬化の進行を促します。
病態生理にはいくつかの機序が関与します。持続する高血糖は終末糖化産物(AGEs)の蓄積を招き、これが血管壁のコラーゲンやエラスチンと架橋して、動脈の弾力性を低下させます。高血糖はまた酸化ストレス経路を活性化し、内皮細胞を直接傷つける活性酸素種を生じさせます。さらに、T2Dには慢性の軽度炎症や脂質異常症がしばしば伴い、血管の安定性を損ないます。総じて、小〜中動脈に進行性の損傷が起こり、血管壁へのカルシウム沈着が進みます。
高血圧:慢性と発作的ダメージ
高血圧は、脳小血管病のもう一つの重要因子です。持続的な高血圧は血管壁へのせん断ストレスを高め、内中膜の肥厚を招き、石灰化を加速します。とはいえ私自身は、慢性高血圧と正式に診断されたことはありませんでした。では、どうして放射線診断報告が高血圧性の石灰化を示すのか――最初は矛盾に思えました。
答えは、現在医学で「仮面高血圧」や「発作的スパイク」と呼ばれる現象にあります。糖尿病の方の多くは、夜間・早朝・感情的ストレス時に血圧上昇を経験します。加えて、運動直後には、とくに糖尿病や血管の硬化、小血管の石灰化を抱える人で急性高血圧が起きやすく、血圧が急上昇して通常のようにすぐには下がらず高値のまま推移することがあります。こうした上昇は診察室ではほとんど記録されませんが、24時間の携帯型血圧計で検出されることがあります。証拠は明確で、これらの発作的スパイクは無害ではありません。とりわけ血流の自己調節が繊細な脳では小動脈に機械的損傷を与えます。数十年のうちに、これら一過性のスパイクが蓄積するダメージは持続性高血圧によるものに匹敵します。
画像所見:CTとMRI
私のCTでは、いくつかの脳内小血管に沿って散在する明るい白色の沈着が見られ、典型的な血管石灰化の所見でした。CTはカルシウムの可視化に最適で、高密度の沈着を高感度に検出します。
一方、MRIはカルシウムそのものを直接強調はしませんが、その帰結を示しました。白質の高信号変化、微小ラクナ梗塞、慢性微小血管病の所見です。これらは文献で定義される脳小血管病(CSVD)に一致し、高齢者における虚血性・出血性脳卒中の主要な原因です。
放射線科では、この種の所見を主に慢性高血圧に帰すことが多いものの、私のケースは、長期の糖尿病や加齢でも見分けのつかない画像パターンが生じうることを示しています。30年以上の糖尿病歴と78歳という年齢を踏まえれば、記録上の高血圧がなくても脳血管に石灰化が存在することは十分に考えられます。
その他の寄与因子
糖尿病と高血圧以外にも、私の病歴の要素がこの結果に重みを加えました。加齢そのものがエラスチンやコラーゲンの構成を変化させて血管を硬くします。私が経験した慢性腎臓病(CKD)はカルシウム・リン代謝を乱し、血管石灰化を加速させます。糖尿病にしばしば伴う脂質異常症も、アテローム形成と血管炎症を促進します。
このように、長い糖尿病歴、目に見えにくい血圧スパイク、加齢、CKD、脂質異常症といった複数のリスクが重なると、脳の小血管には容赦ない累積負荷がかかります。最終的には血管の構造的完全性が破綻し、私の場合は出血性脳卒中として現れました。
科学と個人経験の統合
科学的観点から見ると、私のケースは慢性疾患が「非線形・動的・不可逆・累積的」であることを示す、典型的な数理物理学的事例です。
従来医療は、ある一点で測られた単独の危険因子――血糖ならHbA1c、血圧なら収縮期血圧、脂質ならLDL――に焦点を当てがちです。しかし血管石灰化は、単一の検査値や一度の受診の結果ではありません。生化学的・血行動態的・代謝的ストレスが何十年にもわたって相互作用した、不可逆の帰結です。この累積効果は、関連する縦断データがあれば、粘塑性エネルギーモデル(VMT;他のVMT論文やYouTubeチャンネルを参照)で明確に示すことができます。
個人的観点から言えば、私の脳卒中は単なる「不運」ではありませんでした。30年以上にわたり血管が受けてきたストレスの必然的な最終産物でした。直近15年は丹念に糖尿病管理に取り組んできましたが、初期の20年間に受けたダメージは血管系に刻み込まれたままでした。CTに映る石灰化は、過去の生理の「傷痕」にほかなりません。
臨床的意義と教訓
患者さんと医師がここから学べることは何でしょうか。第一に、脳の小血管の石灰化は偶発的な画像所見ではありません。認知機能低下、白質病変、虚血性脳卒中、さらに脳内出血(ICH:出血性脳卒中の一型)と強く関連します。高リスクのマーカーとして捉え、包括的な管理につなげるべきです。
第二に、管理は多面的でなければなりません。厳格な血糖管理は不可欠ですが、それだけでは不十分です。診察室の外でも血圧をモニターし、家庭用や携帯型機器で隠れたスパイクを捉えることが望ましい。脂質を適正に保ち、腎機能を守り、睡眠やストレスなどの生活要因にも体系的に取り組む必要があります。
最後に、私の経験は医療におけるシステム思考の重要性を強調します。糖尿病や高血圧のような慢性疾患は独立したサイロではなく、数十年にわたり相互作用して転帰を形作ります。脳小血管の石灰化は、その相互作用の物理的な具現です。
なお、拙稿No.1350では、物理学の波動理論を用いて高周波の血圧波と低周波の血糖波を比較し、この現象への洞察を示しました。大振幅で高頻度の血圧スパイク(急性高血圧)は血管破裂を引き起こし得ます。一方、数十年にわたり持続する低頻度の高血糖波は、脳を含む血管に累積的で不可逆的な損傷を与えます。
結論
CTとMRIの画像を振り返ると、もはや静止画ではなく、糖尿病と血管リスクとともに歩んだ私の人生の物語に見えます。今回の脳卒中は単発の出来事ではなく、2型糖尿病、発作的高血圧、血管石灰化、加齢が累積し相互に作用した結果でした。
長い糖尿病歴を持つ方へのメッセージは明確です。血糖管理はもちろん、血圧を注意深く監視し、脂質をコントロールし、腎臓を守り、睡眠とストレスの重要性を尊重してください。医療者にとっては、単一の数値を越え、血管健康を全体的・経時的に捉える視点が求められます。
この脳卒中から私は、疾患の「年」や「十年」ごとの影響がすべて意味を持ち、日々の管理の積み重ねが重要であることを学びました。脳は私たちの過去の生理を忘れません――血管内に埋め込まれたカルシウムとして、その記憶を抱えているのです。
付録:VMTに関する説明
粘塑性エネルギー理論(VMT)は、疾患を「累積的・非線形・時間依存・不可逆」として捉える数理物理学的枠組みで、材料がストレス下で破壊に至る原理と同じ発想に基づきます。統計の限界を越えて健康アウトカムを理解するための動的システムアプローチを提供します。
VMTの詳細は、YouTubeで “Health Talk with EclaireMD” を検索してください。
免責事項
本内容は教育目的の参考情報であり、医療アドバイスではありません。本資料により医師―患者関係が成立することはありません。本要約は自由に共有できますが、改変したり、自作として再公開したりしないでください。
#eclairemd #healthtalk