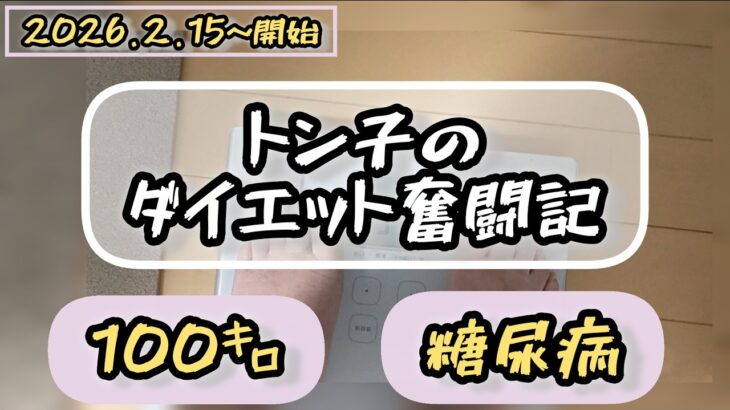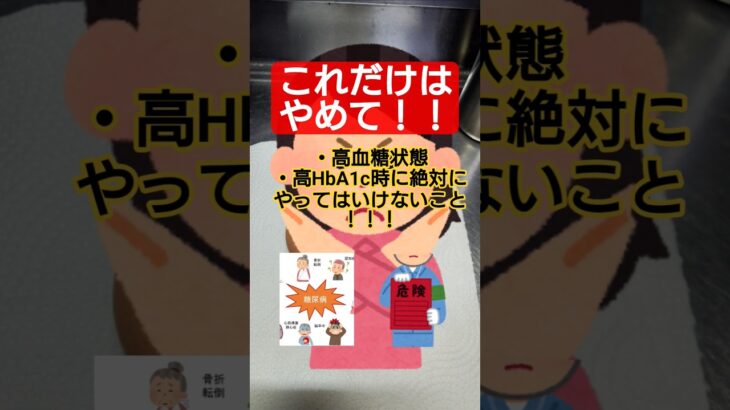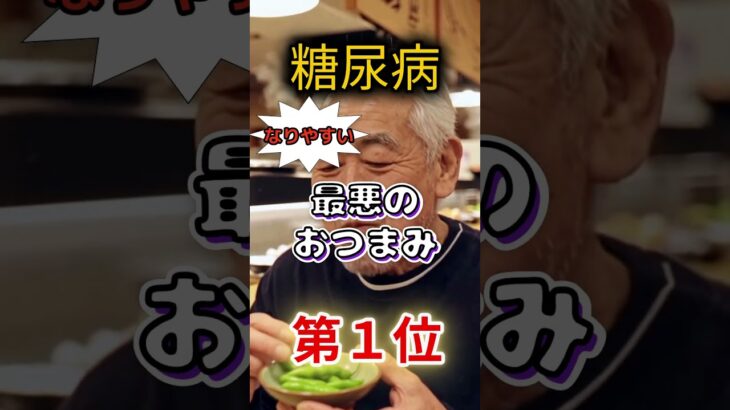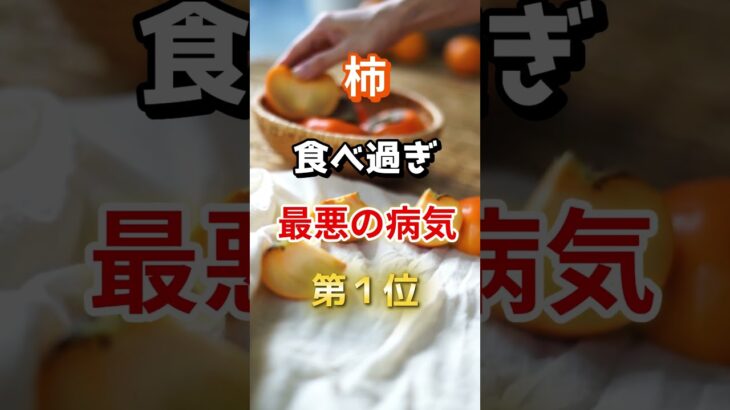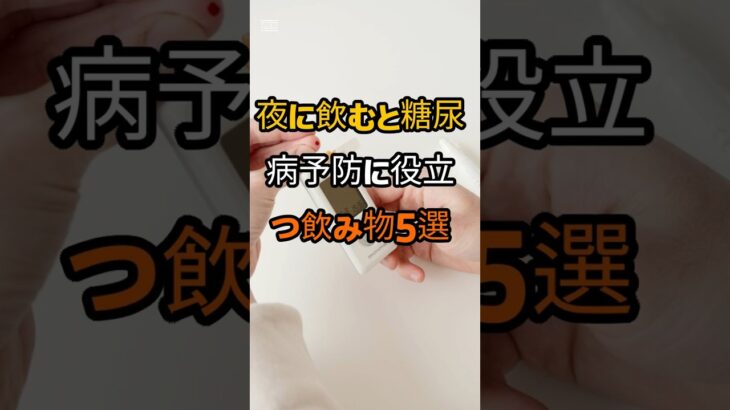抗老化研究の最前線を玉川徹氏が取材しました。
■老化細胞が蓄積し発病も “悪い老化”とは
玉川氏
「順天堂大学の医学部に来ています。抗老化の方法の中に老化細胞を除去するという手法がありますが、この老化細胞の除去を既存の薬でできるんじゃないか。さらに、臨床試験に今、進もうとしているということなので、今から話を聞いてきます」
順天堂大学大学院の南野徹教授は、抗老化について30年以上も研究を続ける第一人者です。
2022年取材
玉川氏
「先生は老化は病気に入れていいと思っていますか?」
南野教授
「病的な老化というものは病気だと思いますね」
南野教授が治療を目指している病気を引き起こす老化。そもそも、老化とは一体どういう現象なのでしょうか。
2022年取材
玉川氏
「老化というのは、体の中で細胞に何が起きている?」
南野教授
「染色体に傷が入って治らなくなると、それに伴ってもう分裂できないようにプログラム化されていますので、細胞一個一個がダメになっていく老化していく」
玉川氏
「その老化した細胞が分裂しなくなった細胞ということでいいんですか?」
南野教授
「そうですね。老化細胞というのは本来、我々の白血球とかによって取り除かれることが多いんですけど、完全に取り除かれないで、だんだんたまっていくと悪い老化になる」
南野教授によると、ヒトの細胞は染色体に傷が入るなどの理由で分裂ができなくなると、老化していきます。
老化細胞が蓄積することで慢性炎症が起き、血管なら動脈硬化、内臓脂肪なら糖尿病など、体のあらゆる部分で加齢に伴い病気が発症するというのです。
2022年取材
南野教授
「比較的思いつく年をとって増える病気ですね、ほとんどが我々がターゲットにしているような老化細胞が蓄積していることが知られていまして。そうすると、それを除去すると、一網打尽的に加齢関連疾患、いわゆる老化という、特に病的な老化に関しては治療が可能になるんじゃないかなと思っています」
■糖尿病治療薬で老化細胞を除去 仕組みは?
そこで南野教授は8月から、老化細胞を除去する新たな臨床研究を開始しました。
患者に投与するのは、ある病気に対してすでに使われている“意外な治療薬”です。その“意外な治療薬”とは何なのでしょうか?
玉川氏
「新しい抗老化の手段というか、研究が今行われているということなんですけれども、具体的にはどういうふうな研究になりますか」
南野教授
「SGLT2阻害薬という薬で、老化細胞が除去されるということを最近見いだしたわけです」
玉川氏
「そのSGLT2阻害薬、これはどういう薬。もともとある薬なんですか」
南野教授
「はい。SGLT2阻害薬というのは、もともと糖尿病の患者さんのために開発された薬です」
南野教授が選んだのは現在、糖尿病の治療に使われている薬「SGLT2阻害薬」です。
これまでに多くの糖尿病患者に用いられてきた薬剤を使って老化のスピードを遅らせようというのです。
南野教授
「SGLT2というのは簡単に言うと、腎臓にある糖を再吸収する穴みたいなものですね。そういうものを(阻害薬で)ブロックすることで、あえて尿に糖を出すことで血糖を下げる」
玉川氏
「血糖の中に糖がいっぱいあるから、尿に漏れてきて、もともと糖尿病と言っていたわけですよね。むしろ、どんどん尿に出すことによって血中の糖を減らそうという薬」
南野教授
「非常にある意味ダイナミックな面白い薬です」
SGLT2とは腎臓にある物質で、尿の中に含まれる糖分を再吸収する役割をしています。
糖尿病の治療では、薬剤によってSGLT2の働きを阻害することで、糖の再吸収を防ぎます。そして、糖を尿として体外に排出して、血糖値を下げているのです。
南野教授は、この糖を排出する仕組みに注目しました。
玉川氏
「糖尿病の薬がなぜ老化細胞の除去につながるのか」
南野教授
「それも非常に面白くて、そもそもカロリーを制限すると寿命が延びるという古くから言われていることがある。同時にカロリーを制限すると、老化に伴って体に蓄積してくる老化細胞のスピードも落ちることも分かっている。SGLT2阻害薬は、いわばカロリーをある程度、外に出す」
■なぜ糖尿病治療薬で老化細胞が減る?
糖尿病治療薬を使った老化細胞除去。動物実験では、その効果が確認されました。
南野教授
「これがマウス実験の結果でして、青い部分が老化細胞。それがSGLT2阻害薬を投与しておくと、(投与から)1週間ぐらいですけどかなり薄くなって、老化細胞が除去されていて、もちろん結果的に糖代謝やインスリン抵抗性が改善してくる」
玉川氏
「どれぐらい減ったという感じになるんですか」
南野教授
「半分ぐらいですかね。ただ老化細胞はがん細胞と違って、半分減ればかなり効いたことになりまして、いろんな病的な老化形質がそれだけでだいぶ改善しますね」
動物実験では、肥満にさせたマウスにSGLT2阻害薬を投与しました。その結果、内臓脂肪にある老化細胞が減少し、糖尿病や動脈硬化などの改善がみられました。また、早老症マウスでは寿命の延長も確認されました。
では、どうして糖尿病治療薬を投与すると、老化細胞が減ったのでしょうか?
南野教授によると、薬剤によって糖が排出されたことで、空腹のような状態になり、体全体がエネルギー不足になります。
すると、体内に蓄積されていた老化細胞もエネルギー不足になり、性質が変わって、免疫によって取り除かれやすくなります。その結果、免疫細胞によって、老化細胞が除去されるというのです。
玉川氏
「直接薬で殺すんじゃなくて、免疫が取り除いてくれるということ」
南野教授
「その方が直接殺すよりも副作用が少ないというふうに考えられる」
■さまざまな病気改善の可能性も
南野教授によると、糖尿病治療薬を使った抗老化研究は、世界中で行われているといいます。
玉川氏
「糖尿病の薬が抗老化にという話は別なところでも聞いたことがあって。メトホルミンという。これと似た感じなんですか」
南野教授
「そうですね。メトホルミンも、このSGLT2阻害薬と全く標的が違うんですけども、似ておりまして。メトホルミンも全体的にはカロリーを制限した時に(免疫が)活性化されるような細胞内シグナルを強くする薬だと言われています。少なくとも一部はカロリーに関係して、抗老化作用、加齢関連疾患に広く効くというふうに考えられていますので、やっぱり糖尿病と老化というのはもう本当に非常に密接で、ある意味カロリー制限と似たような作用を示す(抗老化の)薬があってもおかしくない」
糖尿病の治療薬を使って糖を排出することで、老化をはじめ、加齢に伴う心不全や認知症など、さまざまな病気を改善する可能性があり、世界中で研究が進んでいます。
■ヒトでの臨床研究を開始
玉川氏
「この研究が興味深いのは、臨床試験に入るってことなんですよね」
南野教授
「そうなんですよ。患者さんのリクルートメント(募集)を始めています」
玉川氏
「今始めている」
南野教授
「はい」
玉川氏
「その患者さんというのは、どういうヒトが対象になるんですか」
南野教授
「今回はですね、まず65歳以上で、もうすでに保険で認められている疾患ですね。対象疾患である心不全・腎不全・糖尿病の患者さん」
玉川氏
「糖尿病のない心不全・腎不全の方は対象になるんですか?」
南野教授
「なります」
順天堂大学では8月から、ヒトでの臨床研究を開始しています。対象となるのは、65歳以上の糖尿病・心不全・腎臓病などの患者50人。そのうち25人は、これまでの治療と併用してSGLT2阻害薬を投与。残りの25人は、これまでの治療のみ行います。治療期間は1年間で、その後、効果を検証します。
玉川氏
「臨床研究をやって、その結果なんですけども、何をもって老化細胞が除去できた、抗老化に資したというふうに判断するんですか」
南野教授
「染色体の修飾(遺伝子の変化)ですね。それを調べることで、本来の暦の年齢じゃない、その方の体の年齢というかですね、いわゆる血管年齢みたいなものが分かるようになってきたんですね。それで治療の前と後で推定される、いわゆる生物学的年齢がどれくらい変化するか。当然1年みれば1歳増えるわけですけど、それが増えないとか。むしろ減るとかいう効果がないかどうかというのを確認する」
(「羽鳥慎一 モーニングショー」2025年11月13日放送分より)
[テレ朝NEWS] https://news.tv-asahi.co.jp